介護士である私は、仕事ではもちろん家族である祖父や祖母の入浴介助をしていたので、入浴介助の経験は長いです。しかしそんな私も最初のころは何もわからず始めてしまい、危うく怪我に繋がりかねない失敗もしてきました。
今回は私の家族への入浴介助の体験と施設での入浴介助の体験の2つを踏まえて、新人介護士向けに、入浴に関してのポイントと注意点をまとめました。
Contents
入浴介助の負担を軽減するための心構え
清潔を保つことは利用者さんの気分転換にもなりますし夜も眠りやすくなるなど、お風呂はいいことだらけです。ですが水場でのお仕事は多くの危険も伴うので、安全には細心の注意を払う必要がありますね。
本人の希望を確認してみる
多くの人々は入浴を気持ちよいものだと認識していますが、一方で入浴を面倒なもので、苦手意識を持つ方々もいらっしゃいます。そういった方々もいることを念頭に、入浴介助をする前はご本人の希望をまず伺い、入浴の必要性やメリットを理解してもらうことから始めましょう。
体調が悪いときは入浴しなくてもよい
入浴は清潔が保たれ、気分転換にもなるというメリットがある一方、体に思ったよりも負担がかかる行為です。故に利用者さんの身体に傷がないかなど皮膚の状態を確認するなど、利用者さんの事前の体調はしっかり確認しましょう。
もしも体に不調があるようでしたら、無理に湯船に浸からせることはせず、蒸しタオルなどで体を拭いてあげるだけにするなど、利用者さんの体調にあったケアを心がけましょう。
本人ができることはやってもらう
全てのケアに通じることですが、利用者さんが自身でできることはある程度やっていただく、という意識も大切です。利用者さんができるとおっしゃることは基本的には見守り、洗いにくい部位、例えば背中などだけ、それと無く手伝うなどの気配りをしつつお手伝いをすると良いでしょう。
入浴前に準備するもの
利用者さんの着替えやバスタオルの用意は事前に済ませておきましょう。他には
・替えのおむつ
・入浴後の保湿剤
・転倒防止マット
・シャワーチェア
・シャンプーハット
・爪切り
介護士側は
・防水エプロン
・滑りにくいゴム製のサンダルや長靴
・介護用手袋
等を用意しておくといいでしょう。
入浴前の注意点
気温差がないように、浴室のシャワーを出しておくなどして室内を温めておきます(25度ぐらい)。
お湯の温度も40度ぐらい、夏なら38度ぐらいが適温です。
浴室用の椅子なども、冷たいままだとご利用者が驚いてしまいそのまま転倒につながることもあるので、お湯をかけて温めておいてください。
2. 入浴中の注意
脱衣場と浴室との温度差はないようにしましょう。そして温めた椅子に座ってもらいます。お風呂はリラックスできるなど高齢者にとってもいいことが多いですが、危険も多いので場合によって対応します。
入浴中の介助
・しっかり座ってもらい、手すりがあるのなら持ってもらいます。
・最初、かけ湯やシャワーなど、基本的に心臓に遠いところからかけ始めます。まずは足元にお湯を優しくかけて、お湯加減を確認してもらってください。
・頭を洗ったあと、身体を洗います。
・浴槽につかります。座っている椅子と湯船が同じ高さだと入りやすいです。
介護の基本は『末梢から体幹へ』です。ですから、かけ湯やシャワーなども手足の先から徐々に上へ上へとかけていきます。
特に心臓に負担のある方は温度変化には気をつけないといけないですから、いきなり上半身にお湯をかけることはやめましょう。
また、ここでもできることはなるべく自分でやってもらいますので、自分で洗えるところは洗ってもらいます。
そして一番大変なのは浴槽へ入ることではないでしょうか。1人で入れるための補助器具や、介助を必要とする人のための補助器具もいろいろあります。
入浴の便利グッズ
浴室で使う椅子のタイプはたくさん種類があります。シャワーチェアーや入浴椅子など呼び方も様々です。
椅子の種類
・フラットな椅子(浴槽に出入りが楽なタイプ)
・背もたれがついているもの(背もたれがあると身体を洗う時、安定感があります)
・背もたれとひじ掛けがついているもの(ひじ掛け部分が上がると、そのまま浴槽にも入りやすいタイプのものや、折り畳みができるものもあります)
・浴槽内椅子(浴槽に入れて段差を少なくすることや、座りやすくなります)
・浴槽のフチに設置できる手すり(それを持って浴槽に入ります)
・入浴台(浴槽のフチにつけることで座りながら浴槽に入れます)
また車椅子のようなコマがついているタイプもあります。はっきりした色の椅子が多いのは、高齢者は視力が低下するのでわかりやすくするためです。
これは私の経験談ですが、私の祖父母は割としっかりと座れたことから、背もたれのないフラットな椅子を用意しました。利用者によって使いやすい椅子の形状は違うことを覚えておきましょう。
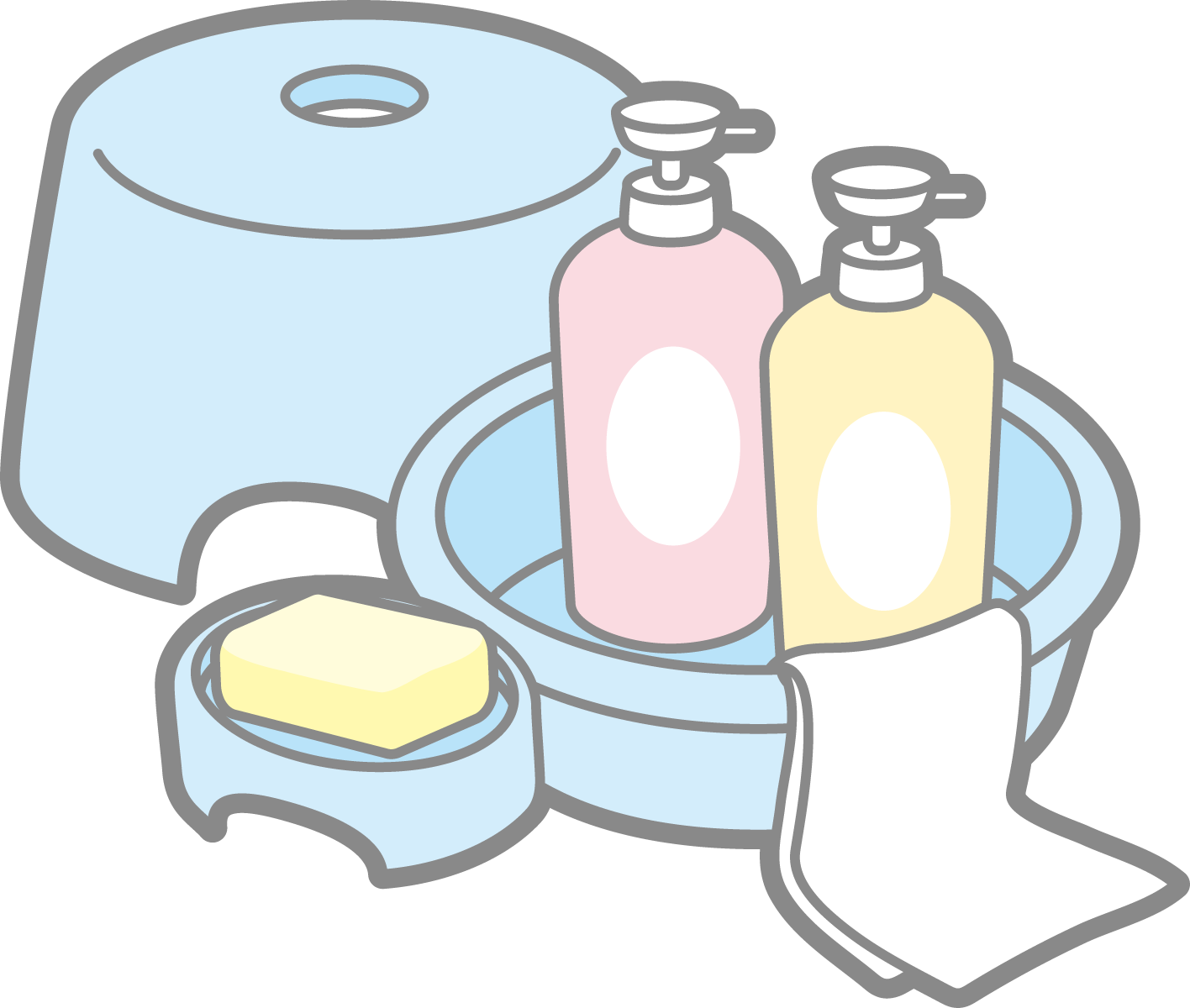
入浴後の介助
3. 入浴後の注意
出てからもしっかりとした椅子に座ってもらったほうが安心です。あるいはしっかりと拭いてから、着替えるときだけでも椅子に座ったほうがいいです。めまいやふらつきなどないか気をつけてあげてください。
入浴後にすること
・浴室を出る前に軽く体を拭きます。
・あまり長くなると負担になりますから、長くても15分ぐらいで済ませます。
・脱水にならないよう、水分を取ってもらいましょう。
・柔らかくなっているので爪を切るのにはいいタイミングです。
・着替えもできる限り自分でしてもらいます。前後ろがわからないなどあれば手伝います。
入浴介助に関するよくある質問
入浴介助で大変なことは?
やはり利用者さんの着替えを手伝ったり、浴室までの移動などで体を支えたり体を洗うことによって足腰を痛めたりすることも多いです。そもそも湿度も温度も高い環境でのお仕事ですので人によっては苦痛を感じるでしょう。
また、濡れた浴室内ではいつもよりも転倒リスクも高まり「転倒や事故を起こせない」というプレッシャーがより掛かることから、心理的にもほか業務より辛いと感じることもあるでしょう。
入浴介助のときの入浴時間の目安は?
湯船につかる場合は心臓への負担を避けるために胸までにし、だいたい五分程度が目安です。それ以上だとのぼせてしまう可能性があります。
入浴介助をする上で注意することは?
・入浴介助中はご利用者から目を離さないようにしましょう。浴室での転倒などはもちろんのこと、入浴中に溺れることなどもありえますので、事故防止のためにも視線は利用者に常に合わせた状態にしましょう。
また、入浴介助中は利用者の全身の皮膚を目視できるタイミングでもあります、普段は服で隠れているようなところに傷やあざがないかは確認し、もしも発見した際は看護師につなぐなども意識すると良いでしょう。
・食前・食後の入浴は避けましょう
空腹状態で入浴をすると貧血になったり、低血糖状態になってしまうことがあるようです。
また食後すぐに入浴をすると、消化の為に血液のめぐりが悪くなり30分~1時間前後は低血糖を起こしやすくなっています、酷い場合は失神してしまい、転倒などの事故につながるので避けましょう。
4. まとめ
何をするにも「お湯をかけるますよ。」「頭を洗いますよ。」など、1つ1つ声をかけてからにしましょう。
とは言え入浴介助は人の好みがかなり出る業務だと感じています。我が家の祖父母で言うと、祖母は体重があったことと、本人の希望から湯量を普通ぐらいにしていたのですが、そのあと体重の軽い祖父が入ると浮いてしまって慌てたことがあります。高齢になってくると半身浴ぐらいの湯量がいいと知ったのはあとからでした。また祖父は自分で体を洗っているときに、面倒くさいという理由で「ついでに頭を洗ってくれ。」と言う人でした。入浴もその人の好みが出ますから、なるべく気持ちよく安全に入ってもらいたいものです。

