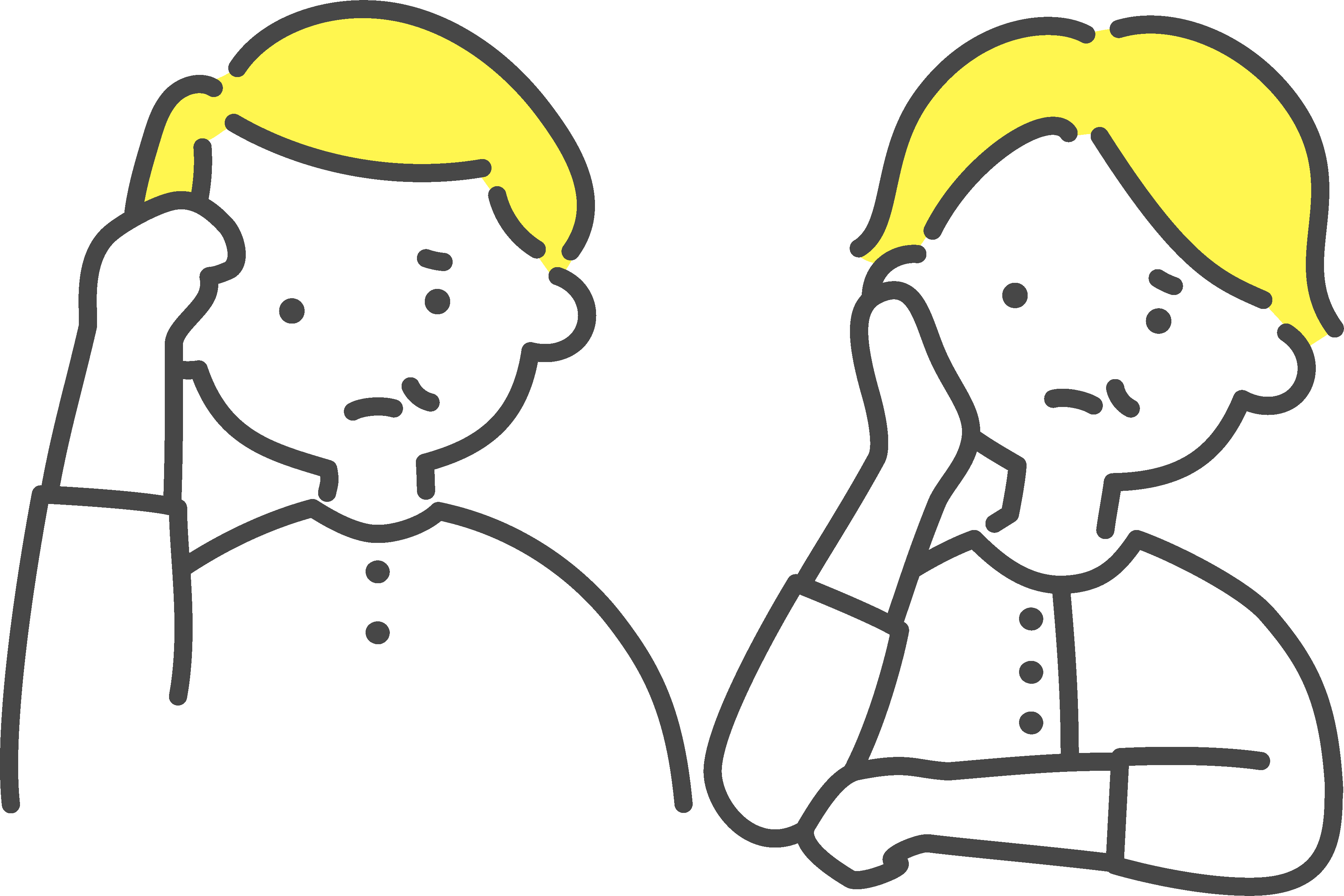
介護施設で行われている身体拘束ですが、最近ニュース等でも耳にする事が多く、虐待のイメージがついてしまいました。
しかし身体拘束とはどういったことをするのか、よくわからない人もいるでしょう。
よくある事例としては、認知症で徘徊してしまう人を部屋から出さないようにしたり、点滴などを抜いてしまうことが無いようミトンを両手にはめたりすることになります。
介護施設で行われている身体拘束ですが、最近ニュース等でも耳にする事が多く、虐待のイメージがついてしまいました。
もちろん介護職員も身体拘束をしたくてしているわけではありませんし、介護保険法に則って身体拘束を行うことはあるのです。
身体拘束を行う場合の手順
介護施設での身体拘束を行う場合の基準としては、
利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為、緊急やむを得ない場合のみ行うことが許されています。
まずはご家族にも事情を説明し、身体拘束の同意書を頂かないとなりません。
また「何故身体拘束を行うのか?」「どういった状況の場合に身体拘束を行うのか?」「どの時間帯で行うのか?」「いつまで行うのか?」等、細かい内容をしっかりと書面にして、家族に記名・捺印を行ってもらうことになるのです。
このような手順を踏まなければ、身体拘束を開始することは出来ませんし、もし家族などに事情も説明せずに始めてしまえば「虐待だ!」と問題になってしまうかもしれません。
緊急やむを得ない状況の基準
緊急やむを得ない場合に該当するのは以下の3要件にすべて当てはまった時のことを言います。
・切迫性・非代替性・一時性
3要件の内容の詳細はどのようなものとなっているのでしょうか。
切迫性
切迫性とは、利用者本人または他の利用者生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い時のことを言います。
治療を拒否する・他者に暴力をふるう・認知症で理解出来ず命の危険があるような行動をとってしまうとき等が考えられる状況となるでしょう。
非代替性
非代替性とは、身体拘束以外に方法がない状況のことを言います。
身体拘束を考えた時は必ず代替案がないか、最後の最後まで職員で検討します。
あらゆる対処法を試してもうまくいかなかった場合に初めて身体拘束を行うか否かを検討することになります。
誰か一人でも「この方法はどうか?」と言う職員がいるのであれば、必ず試してみる事が必要です。
一時性
最後の一時性ですが、身体拘束は慢性的に行ってはなりません。
あくまでも現在の状況では難しいから行っている身体拘束ですので、改善すれば身体拘束を廃止しなければなりません。
ある程度状態が落ち着いてきているのに、職員都合でそのまま身体拘束をしていることは絶対にあってはならないことですので、必ず「一時的に行う対応」ということは覚えておきましょう。
定期的な検討会議を行うこと
身体拘束は一時的な対応でなければなりませんし、なるべく早く身体拘束が廃止出来るよう職員は努めて行かなければなりません。
その為身体拘束をしている利用者がいる場合には、身体拘束廃止委員会等の設置を行い、定期的に廃止を行う為の話し合いを行わなければなりません。
そして内容についてもしっかり書面に残し、記録していかなければならないことが決められています。
特に2018年の介護保険の法改正では、身体拘束を行っている介護施設等で決められた手順を守っていない介護施設には、介護報酬が減算されることも決まりました。
今までの対応では身体拘束の記録等があいまいになっていた背景もあるのでしょう。
また、報酬減にならないよう身体拘束廃止を推進していく施設が増えるようにといった狙いもあるのでしょう。

まとめ
身体拘束は基本的に執り行わない事が原則となっていますが、生命に危険が及ぶ場合にのみ行うことが認められています。
しかし切迫性・非代替性・一時性の三要件にしっかり当てはまっているかを確認し、必ずご家族に了承を得ることが必要になります。
ただ、非代替性については各施設によっての判断になりますので、介護職員の知識や経験で代替え案があるのかどうかが決まってしまう事があります。
施設内に1人でも経験豊富な介護職員や、外部研修等で身体拘束について学んでいる介護職員がいれば、身体拘束をしなくても施設で過ごせる利用者が増えることになります。
是非、身体拘束について学んでおきましょう。

