介護保険制度導入後、高齢化社会において介護保険制度の利用は必要不可欠なものとなっています。また、地域包括ケアシステムの構築も進んでおり、介護保険制度上と地域包括ケアシステム上においてケアマネジャーの存在意義は非常に重大なものとなってきています。
今回はケアマネジャーが利用者の支援を行うためのケアマネジメントについて記載します。

Contents
ケアマネジメントとは
ケアマネジメントの定義
ケアマネジメントの定義はさまざまですが、厚生労働省「障害保健福祉士主管課長会会議資料」では以下のような記述がなされています。
利用者が地域社会による見守りや支援を受けながら、地域での望ましい生活の維持継続を阻害するさまざまな複合的な生活課題(ニーズ)に対して、生活の目標を明らかにし、課題解決に至る道筋と方向を明らかにして、地域社会にある資源の活用・改善・開発をとおして、総合的かつ効率的に継続して利用者のニーズに基づく課題解決を図っていくプロセスと、それを支えるシステム
ケアマネジメントの目的
ケアマネジメントとは、居宅介護支援のことで、要介護者が介護支援のサービスを適切に利用できるようにするために、利用者の状況や周辺環境、希望を考慮し、利用計画の作成や見直し、そしてサービス提供者との調整連絡を行うことです。
居宅介護支援となっておりますが、自宅だけを指すものではありません。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホームなどの介護施設も含め、居宅介護支援となります。
ケアマネジメントで大切なこと
ケアマネジメントの目的は、「人間の尊厳」を守り、「自己決定」と「自立」を支えることです。具体的には以下の点が重要だと考えられています。
1. 利用者の自立支援
ケアマネジメントは、支援や介護が必要な方が住み慣れた地域で自立した生活を送れるようサポートすることを目指しています。
2. 生活の質の向上
本人および家族(介護者)の生活の質を向上させることも重要な目的の一つです。
3. 適切なサービス提供
利用者の心身の状況に応じた介護サービスを一体的に提供し、高齢者自身によるサービス選択を可能にすることを目指しています。
4. 総合的な支援
利用者の生活全体を総合的に捉え、多様なサービスを適切に利用できるよう調整することが目的です。
5. 利用者の権利の保護
利用者の権利を守り、自己決定を尊重することも重要な目的の一つです。
要するにケアマネジメントを通じて、支援や介護が必要な方々が「自分らしく生活する」ことを実現し、本人および家族が尊厳ある生活を送れるようサポートすることが最終的な目標であり、大切なことです。
介護支援専門とケアマネジメントの関係
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者や要支援者の人の相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられるように介護サービス等の提供についての計画であるケアプランの作成や、市町村、介護サービス提供者、施設などとの連絡調整を行うことが役割です。
利用者の生活の質(QOL)の維持・向上を目的とし関係機関と協力関係を構築しながら利用者の暮らしをサポートすることがミッションです。
また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交付を受けた者とされています。
介護保険制度上の高齢者福祉の分野において中心的な役割を担う存在で、高齢化社会のキーマンとなる存在です。
ケアマネジメントの過程

介護支援専門員(ケアマネジャー)のケアマネジメント業務にはインテーク、アセスメント、ケアプラン作成、支援目標の設定、モニタリングの大きく5つの業務があります。
それでは、業務プロセスごとに詳しく解説していきます。
インテーク(相談受付)
インテークは、利用者とケアマネジャーや相談員が同じ課題意識を持って共に歩み、継続的な支援を円滑に行うための第一歩です。
現在の使用者の生活状況や心身状態、支えてくれる人の存在などの確認と意向を整理します。
相談に至るまで関わりを持ってもらえた方々(家族、近隣住民、主治医、民生委員など)がいる場合には、その方々からの情報や見解も確認した上で相談援助を行います。
利用者を含めた関係者間での同意が得られれば居宅介護支援を開始するための契約を結びます。
アセスメント(課題把握)
介護現場におけるアセスメントとは、利用者の生活状況を確認し、相談内容から考えられる支援内容を把握します。
そして把握した情報と相談内容から分析を行い、なにが求められているのかを正しく正確に知ることを目指します。
利用者自身も自覚できていない課題を把握し支援内容とニーズを導き出します。
アセスメントは、利用者にマッチしたケアプランの作成を行うにあたって、非常に重要な業務です。同じ介護度でも利用者さんの生活環境、身体状況、希望や要望によって、最適とされるケアプランや介護サービスは変わってきます。柔軟で適切なケアマネジメントのため、正確なアセスメントが求められるのです。
ケアプラン(原案)の作成
アセスメントから得られたニーズや課題を基に、利用者の意向に沿う目標達成に向け、利用者や家族、介護支援専門員、関係事業者などがひとつのチームとなり、ケアプランと呼ばれる介護サービス計画書の原案を作成します。
ケアプランには大きく3種類あります。
1つ目が居宅サービス計画です。要介護1〜5の認定を受けた方向けのケアプランで、在宅介護をする方全般を対象とした介護サービス全般を指し、訪問、通所、短期入所、その他の4種に分類されます。これらのサービスを受けるために必要となるのが、居宅サービス計画です。
2つ目が施設サービス計画です。要介護1〜5の認定を受けた人を対象とするケアプランで、ケアマネージャーによって作成されます。
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つの介護サービスを利用するために必要です。
それぞれの施設で介護度に応じての入居要件があります。
3つ目が介護予防サービス計画です。
チームマネジメントを行う上で介護支援専門員には、ニーズや課題に対する情報と必要な支援方法を整理し、ニーズの充足や課題解決に向け必要な専門職への依頼を行うことが求められます。
利用者は高齢のため多くの疾患を併せ持っていることが多く、疾患、既往歴、服薬内容などの確認を行い、同行受診などを通じ主治医とも顔の見える関係を作ることもチームマネジメントとして重要です。
ケアプランの実施・管理
ケアプランの実施・管理は、作成した計画を実際のサービスとして提供し、適切なプランになっているかを確認する重要な工程です。
この時ケアマネは、利用者と介護サービス提供事業者間の間に立ち、調整やモニタリングを行います。
ケアプランの実施・管理の具体的な流れ
1. ケアプランの承認と契約
サービス担当者会議で合意を得たケアプランは、利用者と家族の正式な承認を受けた後、各サービス事業者との契約締結が行われます。
契約時には次の点を確認しましょう
・受給者証への契約日記載と押印の有無
・サービス事業者による重要事項説明の実施状況
・利用料金の明示と同意
2. サービス開始時の同行支援
初回サービス提供時にはケアマネージャーが同行し、利用者の不安の軽減とサービスが適切に実施できているかを確認します。特に認知症や身体障害がある場合、それを踏まえた適応な支援が重要です。
3. 継続的なモニタリング
サービス開始後は「月1回以上の訪問」を基本に、以下の項目を確認します。
・サービスが計画通り実施されているか
・利用者の健康状態や生活環境の変化
・新たに発生した課題やニーズ
・サービス提供事業者との連携状況
計画の途中で生じる課題に対応するため、ケアマネージャーは常に「利用者の生活の質向上」という視点を持ちながら、柔軟な姿勢で臨機応変な調整を行う必要があります。
定期的なモニタリングと迅速な対応が、適切なケアを持続させる鍵となります。
支援目標の設定
支援目標は、利用者が同意しており、具体的な目標で達成可能であることが重要です。居宅サービス計画書には「○○したい、□□できるようになりたいから△△の支援を利用して、××のように取り組んでいく」と記載することで、作成したケアプランを通してチームの意識統一が図れるようになります。
支援目標には、長期的目標と短期目標があります。
長期目標は「将来こういった生活を送りたい」という長期間をかけて達成していく目標です。最終的な達成地点を意味しています。ゴールに到達するために達成すべき細かい条件のことを短期目標と言います。
モニタリング(再評価)
サービス担当者会議で目標を共有した際、全体として取り組む課題と担当ごとに取り組む課題に分けます。誰に報告・連絡・相談して対応するかを明確にするためです。
介護支援専門員は、利用者の日常生活で起こる喜怒哀楽や人生そのものに寄り添い、日々の積み重ねを大切にする姿勢が大切です。その姿勢が、チーム全体の安心感を生み出すことになります。それほど重要な立場にあることも心しておく必要があります。
終結
ケアマネジメントの終了要件として、利用者様の逝去や医療機関への入院、施設入居、自立による生活状況の変化などが挙げられます。
これらの要因により計画に基づいた介護サービスの提供が不要となった時点で支援は完了します。
ただし注意すべきは、逝去の場合を除き、支援終了が即ち「支援対象外」を意味しない点です。地域を構成する一人として継続的なサポート体制を維持する必要があります。
ケアマネジメントに関するよくある質問
ケアマネージャーになるために大切なことは何?
主任介護支援専門員になるためにはいくつかの条件が設定されています。
1. 現在も介護支援専門員として従事し、
2. 利用者に自立支援に資するケアマネジメントを行えていることを基本としながらも、
3. 例えば実務経験が5年60か月以上あることや、
4. 専門研修のⅠ並びにⅡを修了していること
等が上げられます。
ですので、自然と介護支援専門員更新を終えている人であれば受講資格は概ね満たすこととなりますので、大半の方々がこの条件のクリアを目指すのではないのでしょうか。
ただし自治体によっては、この受講要件に違いが生じている場合がありますので、受講方法も含め自分自身が受講要件を満たしているかどうかということも、事前に県ホームページや研修実施機関等に確認を行うと良いでしょう。
まとめ
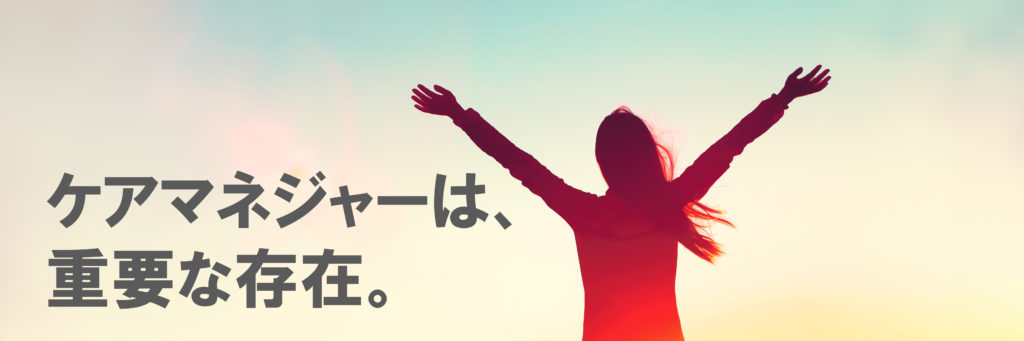
地域包括ケアシステムでは、医療・保健・福祉等関係団体とのネットワーク構築や多職種によるシステムの構築強化が進められています。このシステムを構築していくには、利用者の状況に応じて医療保険や介護保険などの複数の制度を活用しケアマネジメントすることが必要となっています。
ケアマネジメントによって構築された多職種の関係は、支援を受ける方々の生活環境の安定につながり、住み慣れた地域で暮らし続ける安心感にもなります。
ケアマネジャーのスキルアップは今まで以上に求められていますが、その存在は今後の高齢化社会においてより一層の活躍を期待されるものとなっています。
また、ケアマネージャーの転職を考えている方は、ケアマネージャーにおすすめの転職サイト比較にも紹介頂いたリスジョブをぜひご活用ください。
リスジョブは厳選された複数の人材会社に一括登録できるため、その会社しかもっていない好条件求人・レア求人情報が探しやすくなります。全国の数ある人材会社の中から、信頼できる会社のみ厳選いたしましたので、評判の悪い会社や強引な会社はお薦めいたしませんので、ご安心ください。

